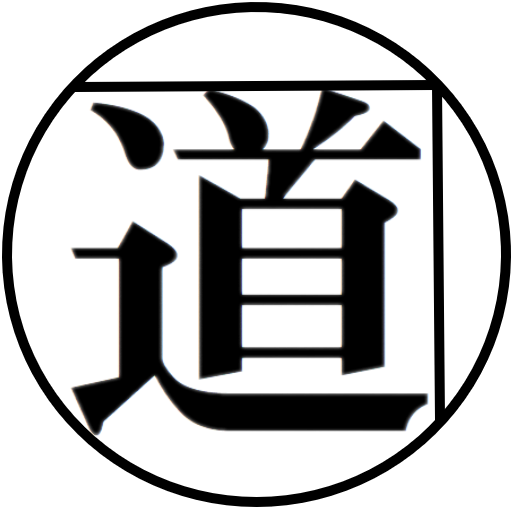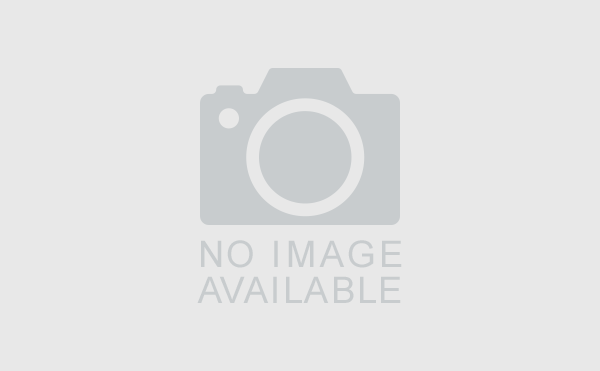お茶鑑定のために嗅覚を鍛えたい。計画編
Contents
日本茶鑑定のために嗅覚を鍛える
茶にかかわるものとして、嗅覚をもっと鍛えたいという思いは常にありました。
COVID-19に感染して味覚と嗅覚が変化するという経験で、嗅覚や味覚は絶対ではないという気づきが自分の中で強くあり、嗅覚をトレーニングする方法を手に入れたいと思うようになりました。
トレーニングなんかよりもどんどんいろんなお茶を飲んだほうがいいのでは?と言われればその通りなんですが、闘茶会を経験したりして思ったのは自分のなかに香りを感じる軸がなさすぎるということでした。
枝豆っぽい…とか、海藻の匂いが…とか、ある程度ふわふわした香りの評価は出せるのですが、第2審査で同じお茶が回ってきてもわからない。全然相対化できていないんです。
いままで生きてきた中で、香りに対して意識的になることがあまりに少なかったなという反省が襲ってきます。
いろいろな香りに実際触れて、自分の中に絶対的な軸になるような香りのインデックスを作りたい。
そのうえでいろんなお茶に触れて、相対的に評価できるようになりたい。
それを実現するためにやりかたを調べてみようと思いました。
ロードマップ
アロマキットを選定する。
いろいろな香りに触れるにはどうすればいいか。
飲み物の香りの先達といえばワインのソムリエ。ソムリエの方々が使っているアロマキットと呼ばれる香料が数~数十種類含まれるセットがよさそうです。
日本茶に使えそうなアロマキットを模索してみました。
検討した結果、aromaster社の24種セットを購入しようかと思います。
嗅覚の基礎トレーニングを図る。
購入する商品は決まりましたが、24種類を自分で選ぶとなるとどう選ぶべきか迷います。せっかく購入するのですから、なるべく無駄なく効果的な「黄金の24種類」を選びたい。
そこで今一度茶の香りと有機化学について学びなおし、どの香りが覚えるべきものかを選定しようと思います。ただ、その間なにもせずにいたらただの先延ばしになってしまって少し寂しい。
そこで購入したのがこちら。
生活の木が販売している、4種類の特色ある香りを意識してかぎ分けることで嗅覚障害を治療することに効果があるのではないかといわれている(持って回った言い方だな)キットです。
12週間続けることが推奨されているので、これで嗅覚の基礎体力を3か月の間つけつつ並行して茶の香りについて座学をしたのち、満を持してaromaster社のキットを購入しようという算段です。
トレーニング・かんたん・記録
今後のロードマップ
24種類を選ぶための道
フレーバーホイールの比較と研究
フレーバーホイールとはある食品から感じられる香りや味の特徴を円状に並べ、香りや味の表現を助けるためにつくられた表のこと。各種のお茶がどのように評価され、どういう香りが鑑定で重視されているのかを見る。なるべく重要な24種類を選定したい。
フレーバーホイール集めてみた
- お茶の香りに関する本と文献を読む
- フレーバーホイール上から重要な香りを選び、有機化学的に分類する
ジメチルスルフィド、4-メルカプト-4-メチル-2-ペンタノン、インドールなど煎茶の香りにおいて重要と思われる物質がフレーバーホイール上の項目にどうあてはまるか。
日本茶の香りに特徴的な物質をなるべく(可能なら発酵茶もカバーして)網羅できるようにしたい。 - 実際に購入してみてのレポート
あまりaromaster社からの購入レポートがネット上にないのでやる。
他のアロマサンプルとの比較も可能ならやりたい。